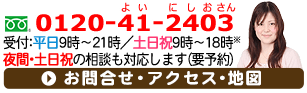「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生(小規模個人再生/給与所得者等再生)のメリット・デメリット
1 メリット・デメリットを知って個人再生を検討
個人再生は、自己破産と違って債権すべてが免責されるわけではありませんが、住宅資金特別条項のようなメリットも多くあります。
しかし、利用するためには、債務者の収入の要件が厳しい・提出書類が多く複雑などといったデメリットもあります。
一口に債務整理といっても、そこには、様々な違いやメリット・デメリットがあり、その特徴を知り、自分にとって一番適した手続きを選択する必要があります。
そこで今回は、債務整理を検討中の方々のために、個人再生のメリット・デメリットについて説明します。
2 個人再生のメリット
⑴ 債務が大幅に圧縮される
個人再生の一番のメリットは、なんといっても借金が減額されることかと思います。
減額率は総債務額や保有資産額などによって変わりますが、一般的には約1/5まで減額されます。
もちろん、個人再生を利用するには一定の要件を満たす必要はありますが、再生計画通りに返済を完了すれば、残りの債務については免責されます。
⑵ 財産を処分せずに債務を整理することが可能
自己破産では、原則として財産を換価して、債権者に分配しなければなりません。
しかし、個人再生では、ローンを払い終えている自動車や持家など財産を処分する必要はありません。
自分の財産を手放すことなく債務を整理することができます。
ただし、所有する財産の額によって、返済額が変わりますのでその点には注意が必要です。
これは、個人再生では、自己破産のように債務者の財産を処分して債権者に分配しない代わりに、自己破産した場合と同額以上の返済を債権者に保障する「清算価値保障の原則」があるためです。
高額な財産があると、返済しなければならない額もより高額になります。
⑶ 住宅ローンが残った持ち家を残すことが可能
自己破産や個人再生においては、債権者平等の原則があるため、一部の債権者を優先した返済は偏頗弁済と呼ばれ、禁止されています。
これに反した場合、自己破産では、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められないことがあり、個人再生では、偏頗弁済の額が清算価値に組み入れられて、返済が増額される可能性があります。
しかし、個人再生では、住宅資金特別条項という特則を利用することで、債権者平等の原則の例外として住宅ローンをそのまま返済し続けることができます。
そのため、持ち家を手放すことなく債務を整理することが可能なのです。
⑷ 職業制限・資格制限がない
自己破産をすると、破産開始決定から免責許可決定まで、保険外交員、警備員、弁護士、税理士、公認会計士など各種国家資格が制限され、この間これら資格を使用することはできません。
一方、個人再生では、職業制限や資格制限がないので、上記のような職業の方でも安心して利用が可能です。
3 個人再生のデメリット
⑴ ブラックリストに掲載される
個人再生のデメリットとして、信用情報機関に事故情報が一定期間掲載されることが挙げられます。
いわゆるブラックリストと呼ばれるものが、これにあたります。
日本には3つの信用情報機関があり、機関によって信用情報の掲載期間が異なります。
ブラックリストに掲載されている間は、クレジットカードを作ることはできませんし、ローンを組むこともできなくなるので、基本的には買い物は現金で一括の決済となります。
⑵ 官報に掲載される
自己破産と同様に、個人再生を行った場合も「官報」という国が交付する広報誌のようなものに、債務者の住所や氏名などが掲載されることになります。
官報に掲載するのは、債権者一覧から漏れてしまったなどが理由で参加できていない債権者・利害関係人に対して、手続きへの参加を促す目的があります。
しかし、一般の方で官報を日常的にチェックしている人はあまりいないと考えられます。
⑶ ローン返済中の自動車は引き上げられる
ローン返済中の自動車には、住宅資金特別条項のような特則はありません。
所有権留保付きのローンを返済中の自動車は、個人再生手続きを依頼した弁護士からローン会社に受任通知が届いた時点で引き上げられてしまいます。
⑷ 返済を継続することができる安定した収入が要件
個人再生では、債務は圧縮されるものの圧縮された債務は返済しなければなりません。
そこで、個人再生をする要件として、返済を継続することができる安定した収入が求められます。
そのため、無職の方や、収入があまりにも少ない方の場合、個人再生を利用できない可能性があります。
実は、個人再生には2つの種類があり、この2つで、債務者の収入に関する要件が異なります。
続いてはこの個人再生の2つの種類について少し解説します。
4 小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類あり、通常は小規模個人再生手続きを用います。
なぜ、小規模個人再生が一般的に利用されるのか、その理由を説明します。
⑴ 小規模個人再生が一般的に利用される理由
- ア 給与所得者再生は、安定した収入がなければ利用できない
-
小規模個人再生における収入に関する要件は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」(民事再生法221条1項)ですが、給与所得者等再生における要件は、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」(民事再生法239条1項)がこれに加わります。
つまり、給与所得者等再生手続きの方が、債務者の収入に関する要件が厳しく、自営業者など収入が不安定な場合は、利用対象にはならないということです。
- イ 給与所得者等再生は返済額が高くなる可能性
-
再生計画では、①最低弁済額、②清算価値(ご自身の資産総額)、③収入から政令で定めた生活費を差引いて求める2年分の可処分所得 を計算し、この中で最も高い金額を分割して毎月返済することになります。
小規模個人再生は、①最低弁済額と②清算価値しか問題になりませんが、給与所得者等再生は③も含めた3つを比較することになります。
上記の中では③が最も高額になりがちですので、小規模個人再生手続きでの返済額よりもかなり多額となるケースが多くなります。
では、どんな場合に給与所得者等再生が利用されるのでしょうか?
⑵ 給与所得者等再生が選択される理由
小規模個人再生は、提出した再生計画について、債権者の頭数の半数以上、または、再生債権総額の過半数を有する再生債権者の不同意があると認められません。
そのため、賛成を得られないことが事前にわかっている場合には、小規模個人再生手続きを申し立てても無駄ということになり、給与所得者等再生手続きを選択することになります。
5 個人再生の手続については当法人にご依頼ください
当法人は、長年債務整理に力を入れて取り組んでおり、豊富な経験や知識を持つ弁護士が多数在籍しております。
あらゆる事案に適切かつ迅速に対応できるよう体制を整えておりますので、借金問題でお困りの方は、当法人に個人再生をご相談・ご依頼ください。
個人再生ができない人とは?失敗しないために注意すべきこと 個人再生手続で載る「官報」とは